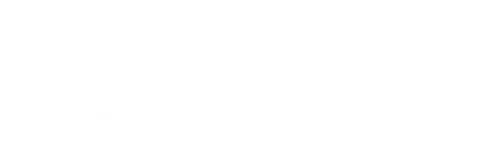こんばんわ。
今回は、従業員50名未満の事業場にもストレスチェック制度の適用が、実施義務化されることに伴い、社労士として、法改正のポイントと実務にあたって押さえておきたい対応をわかりやすく解説します。
1.背景と今回の法改正の内容
制度自体は、2015年12月から「常時使用する労働者が50名以上」の事業場に対して義務化されてきました。 そのため、50名未満の事業場では、「努力義務」とされていました。
しかし、2025年5月14日に改正安全衛生法が公布され、「50名未満の事業場についてもストレスチェック実施を義務とする」旨が明記されました。
施行時期は、公布後3年以内に政令で定める日 とされており、遅くとも2028年5月までには義務化が実施される見通しです。
なぜ、このように拡大されるのかというと、小規模事業場におけるメンタルヘルス不調やストレスによる休職・離職リスクが無視できない状況にあるためです。
実際、50名未満の職場ではストレスチェックの実施率が50%台に留まるといったデータもあります。
2.義務化で押さえておきたいポイント
(1)対象となる事業場・従業員
義務化の対象となるのは、「常時使用する労働者が50名以上」から、50名未満の事業場も含まれるようになるという点です。
ここでの “常時使用する労働者” には、正社員のみならず、契約・嘱託、パートタイム等で「期間が定めのない契約、あるいは1年以上予定されている契約」や、「通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上勤務」の方も含まれます。
このため「小規模だから対象外」という誤解を起こさないよう注意が必要です。
(2)主な義務内容
- 年に1回以上のストレスチェックの実施
- 高ストレス者と判断された場合、医師による面接指導の機会を提供
- 結果の職場集団分析・環境改善
- 実施状況の報告(50名以上の場合) …など
今回の拡大では、特に「50名未満でも義務化する」という点が大きな変更点です。小規模事業場向けには負担軽減の配慮も明記されています。
(3)義務化までの準備期間と社労士が支援できること
義務化時期は政令に委ねられており、2028年までに実施という見通しですが、早めに体制を整えておくことが推奨されます。
社労士として、以下のような準備支援が可能です:
- ストレスチェック実施に関する社内規程・指針の策定
- 外部委託先の選定・契約支援
- 従業員説明・啓発資料の作成
- 個人情報保護・プライバシー確保の体制構築
- 結果の集団分析・報告体制の整備
3.「50名未満」の事業場が今からやるべきこと
義務化が直前ではなく、準備に時間がある今だからこそ、次のステップを進めておくことが重要です。
(1)制度の理解と情報収集
まずは、ストレスチェック制度の目的・実施手順・対象範囲を経営層・人事担当者・管理職に共有しましょう。理解が深まるほど、従業員の協力も得やすくなります。
(2)実施体制の検討
「自社で実施するか」「外部機関へ委託するか」検討が必要です。小規模事業場では専門人材が不在というケースも多く、外部委託による実施が現実的な選択肢となることもあります。
また、実施者(医師・保健師・研修修了者)、実施事務従事者などの役割分担も検討しておきましょう。
(3)社内規程・規則の整備
ストレスチェックの運用に関する社内規程(対象者、実施頻度、結果の取扱い、フォロー体制など)を整備し、就業規則や安全衛生規程への反映も検討すべきです。
社労士として、こちらの諸規程作成を支援できます。
(4)従業員への周知・説明
ストレスチェックの目的や制度概要、プライバシー保護の仕組みなどを丁寧に説明し、従業員の理解と協力を促すことが大切です。手続きが「会社の義務」だったというだけでは協力的な雰囲気は生まれづらいからです。
(5)職場環境改善の意識を持つ
ストレスチェック自体が目的ではなく、そこで得られた結果を活かして 職場環境の改善 につなげることが重要です。少人数の職場では、1人のメンタル不調が職場全体に影響する可能性が高いため、普段から「誰かおかしいな?」と感じたときに声をかけられる関係性づくりも検討しましょう。
4.社労士を活かせるポイント
この法改正は、中小・小規模事業場ほど「早めの対応」が差を生みます。会社として早期での対応が必要になってきます。
- 企業側の不安や疑問(「費用は?」「どう始めていい?」)に対する相談窓口
- 制度導入・運用のロードマップ設計・実務支援
- 従業員にとって安心できる実施体制・個人情報保護体制の構築
- 改正法へ向けた予備的な社内調整・説明
5.まとめ
中小企業・小規模事業場に対しても、ストレスチェックの義務化が予定されているという本件は、単なる“義務対応”ではなく、働き手のメンタルヘルスを守り、職場の生産性や定着率を高めるチャンスです。
是非、制度の趣旨をご理解頂き、改正の動きを「他人事」ではなく、「自社の備え」として捉え、今から準備を始めることをおすすめします。
最後までご覧頂きありがとうございました。
今後も皆様にとって有益な情報を適時提供していきたいと思います。